
こんにちは。ココです。
注意欠陥多動性障害(ADHD)で自閉症スペクトラムな息子の行動と会話から何かのヒントを綴っていく当ブログへようこそ。
さて今回も「作文の書き方・息子流」番外編をお送りします。
テンプレート方法
発達障害の子供たちの作文指導方法として、本によく載っている手法があります。「空」は「青い」、「遊んだ」は「面白かった」とセット、というテンプレート的なものを覚えさせて、もう考えることなくそこに当てはめさせて書かせる、というやり方です。「テンプレート方式」ですね。
私も最初はやらせてみたのですが、書けないけど語彙はたくさん持っている息子にとっては、毎回そんな画一的な文句を使えるか!ってな感じでかんしゃくを起こしていました。
彼なりのプライドがあるようです。
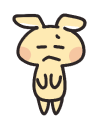
書けないくせにプライドだけは見上げるように高いんだから…。ホント、息子くんの扱いには困っちゃうよねえ…。
あまり文章内容にこだわらないお子さんであれば、ストレスが少なく書ける方法だと思うので、ちょっと書いてみました。
自閉症スペクトラムで決まりきったことを好むタイプであれば、この「テンプレート方式」は本人にとってストレスが少ない作業になるかと思います。
ストレスを軽減させてあげると、不得意意識も少なくなりますよね。

いつも心と頭が満杯な発達障害の子供たちに、「なるべくラクに」作業が進められる方法を探してあげるのは大変なことですが、親としてもその後がだいぶラクになりますから。ここはひとつ、頑張りましょう!
お絵描き物語方法
もうひとつ試した方法があります。状況を絵に描いてあげて、お話しながら作文を仕上げていく、という「お絵描き物語方法」です。
残念ながら私は絵心がなく、逆に息子は絵を描くことの方に没頭しちゃって時間がどんどん過ぎていき、もう作文どころではなくなってしまった…。ということを数度繰り返していたので、この方法はやめてしまいました。

息子には向きませんでしたが、女の子には向いていそうな方法かな、と思ったので紹介しました。知的障害支援クラスの女の子で、この方法がとても良かった!と喜ばれた例もあります。
時間を多く要しますが、それを「親子の勉強兼コミュニケーションの時間」と捉えて付き合った、と女の子のお母さんはおっしゃっていました。
彼女は今は小学校6年生。下級生と動物の世話が大好きな、愛情深い女の子に育ちました。

このお絵描き物語方式で、(知的障害支援クラスの)下級生の絵日記を手伝ったら何とか書けた!と誇らしげにお喋りしてくれたそうです。
「誰かの役に立った」という経験は何物にも代えがたい貴重な経験。彼女の夢は「支援クラスの先生」だそうです。
まとめ
いいヒントになるかどうかは分かりませんが、1人でも1日でも。笑顔が増えてくれたらいいな、と思います。
そしていつか、学校の中でもストレスなく、自分の気持ちをスッと言い表せるようになれたら。
息子の毎回かんしゃく活火山は、休火山に変身できるのではないかな、と思っています。
いつかきっとね。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。