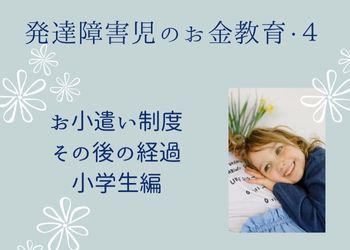
こんにちは。ココです。
注意欠陥多動性障害(ADHD)で自閉症スペクトラムな息子の行動と会話から何かのヒントを綴っていく当ブログへようこそ。
今日はうまく行ったように見えた発達障害児息子のお金教育。その後の経過。
「目標」がないとやっぱり貯められない
いきなり結論から申しますと、発達障害児のお金教育は相当(というか、ものすごーく、もう泣けるくらい)根気と時間がかかるから、やる気になったら早めに始めた方がいいですよ!!ということです…。
100円ちょっとたまると、その場の思い付きでどーでもいいモノを買っては次の日にはその存在さえ忘れている…ということを何度も繰り返した息子。
その後彼は「これは欲しい…!」という、ちょっと頑張れば手の届きそうな商品を見つけ、コツコツお手伝いをし、2ヶ月半後にやっと手に入れる、という貴重な経験をしました。
親からしてみるとすごい成長!

頑張ったよ、頑張った、息子くん…!!と感涙したのもつかの間。
その後冬休みがあり、当時コロナウイルスの影響であっという間にながーい春休みに突入してしまったため、暇を持て余している彼はお手伝いを進んでやるようになりました。

あまりあちこち出かけられないので、お手伝いの種類も増加。
そこに習い事が休みになったり、かと思えば一定期間やり始めたりという状態だったため、「習い事の振り替え130円」も頻繁に登場。
そうして半年前とは比べ物にならないほどのハイスピードで500円、800円とお小遣いがたまっていきました。
ところが。
以前みたいに「これが欲しい!」という目標物が無いと、やっぱり貯められないんですね…。
どんどん「どーでもいいもの」に散財!
ちょっと牛乳を買うためだけに寄ったスーパーで、息子はアニメ「名探偵コナン」のちっちゃなカード付きのガムをいきなり購入。
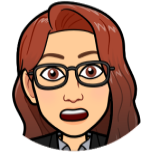
怪盗キッドが出てくるかわかんないんだよ?あいちゃん(女の子のキャラクターです。彼にとってはどーでもいいキャラクター)が出てきたらどーすんの?それにガム、嫌いじゃない

いい。買ってみる
いいって言ってもさ…。目当てのものが出てこないと癇癪起こすじゃない…。
何度か諭したものの、譲らないので諦めました。
お小遣いの使い道はゲームでなければいいよ、とお小遣い制度を始める際に話していましたからね。約束は約束です。
結果は予想通り。癇癪をおこしましたね。
カードのキャラクターは私が見もしないうちに店内のゴミ箱に捨てられたため、何だったのか分かりませんが…。
付随のガムももちろんゴミ箱に直行。ガム、彼は苦手なので…。(ちなみに私も苦手。胃が気持ち悪くなるんです…。だから勿体ない~!!と思いつつもゴミ箱に投下されていくガムを見つめていました…)
もう何のための200円だったんだか…。

ガチャガチャって昔と違って700円とか高額なものも何気ない顔して並んでいるんですよね…。当たるかどうか分からないものにお金を突っ込んでしまうのは、宝くじと同じなのかも…。
その直後ゴミ箱のそばにあったガチャガチャをやる!とまた言い出し、すぐさま500円投入。
イライラした気持ちでいると、イライラするものを引き寄せてしまうものです。またしても要らないものが落ちてきました。
もうたった10分で700円散財。残金35円…。
その後もちょっと貯まるとすぐにどーでもいいものに投入してしまう息子。
これからお出かけする場所の方がもっともっと色々あるのに(遊園地や駅前、水族館など)、トイレに寄ったコンビニですぐ散財してしまいます。
途中までは上手く教育できてたような気がしたんだけどなー…。
ADHDの衝動性はお金に関しても
これはパパに似たのか(金銭感覚のないひとです…)、それとも発達障害の「先の見通しができない」「衝動的な行動が多い」「一気に興味が上限突破、3分後に沈下」な特性によるものなのか、それとも子供って基本こんなものなのか…。
ああ、定型発達の子供を育てたことがないからわからない…!!
定型発達のお子さんを持つお友達に聞いても、まあそういった傾向は男の子には多いものの、ここまでの衝動性はないようでした。
遊園地やアミューズメントパークに行く予定があれば、さすがにそこに着くまでは我慢するようですね。
先の見通しをつけることができるのです。

ディズニーランドに行くからと1000円のお小遣いもらって、さあ電車に乗ろう!という改札口付近でいきなり1000円分ガチャガチャで散財…なんてことはないみたいです。
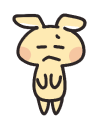
当たり前か…。さすがのパパもそこまで衝動的にお金は使わないからなあ…
それならお金を管理してあげればいいかというと、一度手にしたお金はもう「自分のもの」という認識が強いので、お小遣いをその場に携帯していなくても「415円あったよね。あれで買う!」となります。
無駄遣いだと諭してもダメですね。一旦突っ走り始めた欲望は癇癪と同じ。爆発するまでは自分自身でもおさめることができないようですから。
そう考えると「癇癪」と「物欲」ってベクトルが同じなのかな…と思います。
ひと昔前のように、皆がおなじような金額のお小遣いをもらっていた時代とは違います。小学1年生であっても1万円札を持ってゲームのカードを買いにコンビニまで来る子と会ったりすることもあります。
そんな友達が周りにゴロゴロいるご時世ですから、お金の価値を教育するのはやはり大変ですよね、定型発達児でも。
まとめ
それでも、お金の問題は一生付きまといます。子供たちが天寿を全うするまで、私たち親が面倒を見てあげることはできません。
息子のように一旦習得したかのように見えて、いかりや長介さん調に「だめだこりゃ」とまたなって…。
そんなことを何年も繰り返すことになるのでしょう。
そんな、結果がなかなか見えてこない発達障害児の教育のあれこれ。
でも頑張って続けていれば、十何年か後に意外なかたちで花を咲かせてくれるかも。
「親が子供に残せるのは、愛情と思い出の時間、そして教育だけなんだよ」
まだ学生だった頃に亡くなってしまった私の父が、生前言っていた言葉。
そう。発達障害児にいま一番必要なものは、愛情と教育。そうなんだよなー。
とりあえず、「労働を伴わないとお金は手に入らないということだけは」教育できたかな。お手伝いの報酬5円を小さな手のひらに乗せてあげるたび、そう自分を勇気づけている私です。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。