
こんにちは。ココです。
注意欠陥多動性障害(ADHD)で自閉症スペクトラムな息子との毎日から得た小さなヒントをお伝えしている当ブログへお越し頂き、ありがとうございます。
今回は息子の最大の苦手宿題・「漢字の書き取り」。そんなにかんしゃく起こすならいっそ教材を「手書き」から「タブレット」に変更してみたらどうかな?と思い立ち、早速やってみた息子の体験談をご紹介します。
- どうしても苦手なら「量を」減らしてもらうよう提言する
- 癇癪起こしながら頑張っても「覚えられない」
- 練習量が減ったらテストも散々に
- 学習障害ではないのに「書くことが苦痛」
- 教材をタブレットに変えてみたら?
- まとめ
どうしても苦手なら「量を」減らしてもらうよう提言する
漢字練習の宿題ってきっとどこの小学校でもあると思いますが。息子はこの漢字練習が苦手です。
黙々と同じ作業を続ける集中力がないので、毎回かんしゃくを起こしてしまいます。
あの手この手でしばらくは漢字練習をさせていたのですが。

ある程度効果があったのはこの方法!
ADHD息子は、この方法で4ヶ月は頑張って漢字練習ができました。
あまりに毎日かんしゃくを起こすので、2年生になってからは担任の先生にお話して、通常2ページの書き取り練習を1ページへと変更してもらっていました。
この時点ではまだ発達障害の診断は出ていませんでしたが、日頃の多動全開な学校生活に担任の先生は快く了承して下さいましたね。
このように子供にとって困難な宿題の場合は、担任の先生に相談して宿題の量を調整してもらうといいですね。
お母さん方は意外に宿題の量の調整をお願いすることがないようです。皆さん真面目なんですね。私もそうでしたが…。(笑)
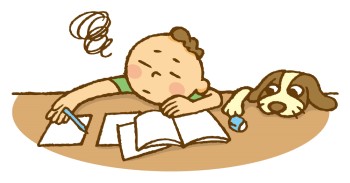
もしあまりにも困難な場合は、思いきって宿題無しにしてもらってもいいかもしれません。
今の小学校は担任の先生にもよりますが、割と寛大にみてくれることが多いです。
癇癪起こしながら頑張っても「覚えられない」
私も一時期そうでしたが、出された宿題は絶対全部やらせなきゃいけない!という変なプレッシャーがありました。
授業も満足に参加できていないんだもの、せめて宿題だけは!みたいな気持ちがあって。
でも、泣いたり吠えたりしながら勉強しても、半分位は覚えられないんですよね。
気持ちが乱れているから、頭に蓄積されていかないんです。
それよりも、量を半分に減らして一気に仕上げた方が本人も覚えるし、こちらも気持ちがラクです。
そして何より激しい癇癪を頻繁に起こしていたこの時期は、勉学よりも本人の気持ちの安定が最優先事項。
こうして2ページだった漢字練習を1ページへと変更してもらい、2年生の時は他の子の半分の量を頑張っていました。
練習量が減ったらテストも散々に
しかし3年生になり、格段に画数や覚えなければならない量が増え、音読みも訓読みも出てくると。1ページ書いていた量が6行になり、2行になり、あっという間に毎日真っ白な状態に…。
それとともに、今まで80点以上は取っていた漢字テストが4分の1も書けなくなりました。

しかも書けた漢字は間違えてる…。
3年生に上がって、たった3ヶ月で坂道をゴロゴロ~っ!と転げ落ちてしまった感じです。
成績がガクンと落ちたことは本人も相当ショックだったようですが、癇癪を起こすばかりで、やっぱり一文字も練習しない…。

思い返せば2年生までの担任の先生は、間違えた漢字は脇に3回書いて再提出、といった指導方法でした。
間違える漢字もひとつふたつ程度だからそれほど苦ではなかったようで、その頃息子はちゃんと書いて提出していました。
彼はその3回練習で、自分が間違えやすい漢字を習得していたのでしょう。だからテストでは満足感のいく結果が出せたのだと思います。

なのに今は一文字も書かん…。覚えないのは当たり前です。
大人でもそうですよね。スマホばかり使っていると、学校の連絡帳を書くときに「あれ?どう書くんだっけ?」と漢字をど忘れして調べることがよくあります。(私だけでしょうか…)
書かなければ、なかなか覚えないんです。
学習障害ではないのに「書くことが苦痛」
しかし、とにかく書くのが嫌い。読み書き障害(ディスレクシア)ではないし、めちゃくちゃな象形文字でもない。
ただ、書くことに非常にストレスを感じているんですね。

頭でまず漢字の「カタチ」を認識し、次にそれを紙に書きうつす。この2ステップある作業が苦手なんです。
これは息子に限らず、学習障害(LD)を併発していないにも関わらず書くことが「非常に苦手」とする発達障害児は結構いるようです。
「漢字のカタチを視覚的に認識する」作業と「いま認識したカタチを紙面に写し取る」作業、そしてその漢字の「読み方」を覚える作業、「意味」を知る作業、「記憶する」作業…。たくさんの作業があるため、頭の中が飽和状態になってしまうんですね。

しかも「はね」とか「止め」とかが曖昧だとバツになるんだよ…。へんとつくりのバランスも悪いとやっぱり「?」とかって赤ペンで書かれるし…。
文字って「だいたい読めれば」用は足りるんじゃないの?
漢字はそんなところがいちいちイライラするんだよ。
教材をタブレットに変えてみたら?
そんなある日。家庭学習教材としてタブレットを導入してみることになった我が家。
それはスクールカウンセラーさんと他愛ないお喋りをしていて「家庭学習にタブレットってどうかな?」という話が持ち上がったとき。
「やってみてー。息子君の様子、聞きたい。うまく行ったら他の子にもアドバイスできるから!」
タブレットかあ…。紙に手書きするのは嫌でも、画面上に書くのは興味を引きそうです。パソコンや機械操作が得意な発達障害児も確かに多い。
「楽しければやるんじゃない?」
単純に考えれば納得です。楽しくないから、苦痛なんですね。
早速痛い出費に泣きつつ、タブレット教材を取り寄せることにしました。
そして息子に漢字をタッチペンでなぞる漢字練習にトライしてもらいました。
するとこれが大好評!ひとつなぞるだけで「ピコーン!」と楽しそうに電子音が鳴り、一文字書き終わると即座に「ポーン!」と花丸が。
間髪入れずに採点される反応の早さと、薄く下書きのある部分をなぞるだけの簡単さが良かったようです。
「お手本を見る → それを覚える → 紙に書く」の、「見る→覚える」という2ステップを飛ばせるので、作業が楽になるのでしょうね。笑顔が増え、癇癪も減りました。

まとめ
突然の高額出費には泣きましたが、かんしゃくが減るという素晴らしい効果にしばらく私も気持ちが軽くなりました。

「最初のうちは」嬉々としてやっていましたが、数ヶ月後にはまたしても癇癪再発でした…。
このお話はまた別の機会に…。
ちなみに息子が購入したのは「スマイルゼミ」という専用タブレット購入型の通信教育です。
学習専用のタブレットなので、ネットを勝手に繋いだりSNSを使ったりという機能が強力に制限されているので、「安心」という基準からこれを選びました。

いきなり通信教育を始めるのはハードルが高いですが、無料の漢字練習アプリも調べてみるとたくさんあるので、まずは市販のタブレットやスマホで試してみるのもオススメですよ。
最後までお読みいただいてありがとうございました。