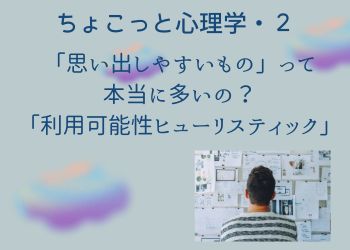
こんにちは。ココです。
注意欠陥多動性障害(ADHD)で自閉症スペクトラムな息子の行動と会話から何かのヒントを綴っていく当ブログへようこそ。
今日は思い出しやすいものを基に確率や程度を推測する方法「利用可能性ヒューリスティック」とそれに関連する「エコーチェンバー現象」についてのお話です。
●「エコーチェンバー現象」とは、「自分と類似した意見や嗜好を持つ人が集まる狭いコミュニティーの中で、同じような意見を見聞きし続けることにより、自分の意見が増幅・強化されていく」現象のこと。
利用可能性ヒューリスティックの実験
「利用可能性ヒューリスティック」。これはイスラエル出身の心理学者エイモス・トベルスキーとダニエル・カーネマンの共同研究で実証されました。
彼らは英語の中にRが最初にある単語と、Rが3番目にくる単語のどちらが多いかを被験者に推測してもらいました。また、別のアルファベットについても同様の推測をしてもらったのです。
その被験者152人中105人もの人がそれぞれアルファベットが最初にくる単語が多い、と予測しました。
実際は3番目にくる単語のほうが多いことが証明されています。
エイモスとダニエルは、最初にくる単語の方が思い浮かべやすいからだと考えました。

確かに「最初に『り』がつく単語」の方が、「3番目に『り』がくる単語」より数段思い浮かべやすいですよね。「3番目に『り』がくる単語」は、ちょっと考えないと思いつきませんから。
思い出しやすいものは「よく起きること」ではない
ニュースを見ていると最近は高齢者の交通事故が多くなった、という印象を受けます。
実際は車の衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速制御装置、車間距離制御装置など、数々のドライバー支援装置が続々と導入されているため、高齢者の交通事故は減少傾向にあるそうです。
しかし「平凡な日常」はニュースにはなりません。

えっ、と驚くような事故は注意を引きやすく記憶にも残りやすいため、何度か同じような事故があることが報道されると「高齢者の事故って増えているんだ」と思い込みやすいんですね。
脳はショートカット機能を使うことを好む
人間の脳は意外とエネルギーを使います。
そのため、自分にとってそれほど重要ではない事柄を考える時、人は経験や直感などを使ってなるべく簡単に考え、ショートカットで判断を下す傾向があります。
その方が「考える」エネルギーを節約できますからね。

近年は思い出すプロセスがはっきりしない(上記のアルファベットの問題など)「利用可能性ヒューリスティック」よりも、個々人の主観や経験をもとに推論する、という意味の「検索容易性」という言葉の方が、よく使われるようになってきました。
「エコーチェンバー現象」にも注意
今やSNSは小学生も日常で使っている時代。
SNSは簡単な方法で全くの他人と繋がることができ、それがきっかけで友達を得たり結婚にまで至ったカップルもいます。
ですがSNSは自分と似た意見や趣味をもつ人が集まる場となっています。人は自分の感情や意見を肯定されることで安心感を得る生き物です。

そうやって思想が肯定され共感され続けちゃうと、まるで自分の意見が一般的な考えなんだ!って錯覚を起こしやすくなるんだよ。
SNSでは多くの集まりの中で自分の考えに賛同するような意見が返ってきやすいため、閉じられた空間で音が反響する様子をなぞらえて、この現象は「エコーチェンバー現象」と呼ばれるようになりました。
こういった現象を踏まえると、SNSという閉じた空間に縛られ過ぎないよう、大人も子供も注意して利用することがこれからの時代の課題となるのではないでしょうか。
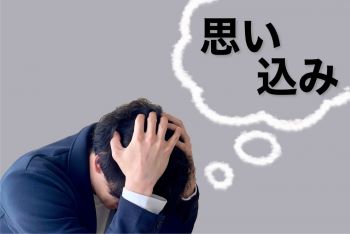
まとめ
今回はあまり耳慣れない言葉「利用可能性ヒューリスティック」と「エコーチェンバー現象」を取り上げてみました。

「利用可能性ヒューリスティック」とは「よく見るものや思い出しやすいものを基準にして簡単に決定を下してしまう思考傾向」のこと!

「エコーチェンバー現象」とは、「自分と類似した意見や嗜好を持つ人が集まる狭いコミュニティーの中で、同じような意見を見聞きし続けることにより、自分の意見が増幅・強化されていく現象」のことです!
SNSやソーシャルメディアに惑わされることのない、柔軟な考えを持っていきたいですね。
ココのちょこっと心理学、お楽しみいただけたでしょうか?
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。