
こんにちは。ココです。
注意欠陥多動性障害(ADHD)で自閉症スペクトラムな息子との毎日から得た小さなヒントをお伝えしている当ブログへお越しいただき、ありがとうございます。
超飽きっぽいADHD全開!の息子は、読書が大好き。
今日はそんな息子目線と、親の私も「これはいい本!」と感動した本をちょっとご紹介したいと思います。
数学嫌いな父が幼少の私に買い与えていた本
私の亡くなった父は勉強が大嫌いだったそうです。
上の兄弟は出来がよかったので、なおさらやる気がそがれていたのかもしれません。
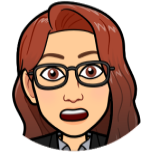
勉強、特に数学が大の苦手だった父は社会人を数年やっていて、何と設計課に配置換え。
一気に測量の道へと走らなければなりませんでした。
三角関数どころか、数学はホントに鳥肌が立つほど大嫌いだった父。
本を買ってもちんぷんかんぷんだったため、当時車で40分ほど離れた所で暮らしていた義理のお兄さん(私にとっては伯父ですね。)のお家に毎週通い詰めていたそうです。伯父は数学の教師でした。

平日は毎日退社後2時間は勉強。
30歳を過ぎて中学生の数学からやり直し始めた父は「算数は積み重ね教科」ということを痛感し、幼少時に「数に今のうち慣れておけるように」と私に「はじめてであうすうがくの絵本」という安野光雅さんの本を全巻買い与えたそうです。
絵本で「算数嫌い」を回避できる!
私自身も数学は得意ではなかったのですが、この本は好きでよく眺めていたそうです。
「算数の本」というよりは、「数の概念」をおもしろおかしく、そして簡潔丁寧に説明してくれる本です。
昭和の頃から何十年も読み継がれた良書です。
「すうがくの絵本」というと、ちょっと「小難しい」ような気がして手が伸びないことも多いようで、意外とこの本を知っているママは少ないですね。
ですが本当に今読んでも分かりやすい!
小人が「まほうのくすり」を作って馬やうさぎにつけ、伸縮の比率を試したり、「きれいなさんかく」では三角形や多角形を見ながら作る折り紙が出てきます。
小さい子のみならず、特に知的・発達障害の子には非常にとっつきやすい本です。

算数障害の子には、特に噛み砕いて「かず」というものを描いてあるので理解度が進むかもしれません。
算数が苦手だな…と思うお子さんには、是非是非読ませてほしいですね。

算数が「小難しい学問」ではなく、「日常にあふれている小さな不思議」なんだ、ということだけでも分かりますから。
数の概念が面白い挿絵で感覚的に会得できる
実家にあったこの本を絵本がわりに持ってきた頃、息子はまさしく「絵の本」としてめくって遊んでいました。
小人の表情とかが面白いようで、よく笑っていましたね。
年齢があがるごとに少しずつ理解できるページが増えるらしく、時折出しては小学校低学年まで何度もめくっていました。
算数は、とかくつまずきやすい教科です。苦手意識も他の教科より強く出やすい。
でも「概念」だけを何となく感じることができれば、苦手であっても「嫌い」にはなりにくいんですね。
息子は文章問題やひとひねりある問題は全然ダメで、算数は「得意ではない」教科ではありますが、「嫌いではない」そうです。

「嫌いではない」。そういうのって、大事ですよね。
まとめ
こんな風に息子の「苦手意識が出てきそう」「つまずきそう」な分野は、そのジャンルの本をあれこれ見て「絵本」や「読み物」として 面白そうな本を探して与えてきました。
昔と違って、今はフルカラーだったり写真が美しかったり、イラストが笑えたり文章がウケ狙い満載だったりと、大人でもグイグイ引き込まれる本がたくさんあります。

学校の授業では面白くなくとも、本の世界で興味を持ってくれたら。「嫌いだから勉強しない!」とはなりません。
授業に参加しなくとも、「興味さえ持ち続けてくれれば」。
だいじょうぶ。授業に何年も参加しなかった息子のように、何とかなります。(笑)
苦手なら、嫌いなら。面白おかしく笑える方向から角度を変えて見せてあげましょう。
おもしろいなら、子どもは喰らいつきます。単純ですが、もっともなことですよね。(^_^;)
その時は点数が思ったほどよくなくても、「それをもっと知りたい」という気持ちがずっとずっと後になって開花するときもあります。
だからまずはできることからサポートしてみましょう。
え??そんな本を探す時間がない??
大丈夫。これから時々、息子目線の「おススメ本」を紹介していけたらなあと思っています。
気になったらこのブログをたまに覗いてみてくださいね!(*^-^*)
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。

