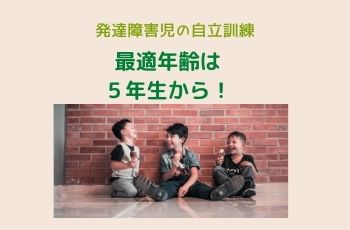
こんにちは!ココです。
当ブログにお越し頂き、ありがとうございます。
さてさて小学生の我が息子、自立なんてまだまだ先なようだけどそろそろ訓練を始めます。
まだ小学生だけど自立訓練??
ランドセル背負って地べた這いつくばって虫を探す息子を見ていると、「自立」なんてものはまだまだずうっと先のような気がしますが。
何かと色々問題有りの発達障害児。
学校の授業の1時間でさえまともに座ってられないのに、高校受験なんて出来るのか??もしかしてもしかすれば中卒で終了ってこともあるかも…。なんて不安がよぎる今日この頃です。
そうなったら単純に逆算してあと4年ちょっと。
何かを習得することに定形発達の何倍もかかる彼ら発達障害児には、4年なんて自立訓練するには短すぎるくらいです。

小学5年生はもうティーンエイジャー
今小学5年生、もしくはそれ以上のお子さんをお持ちの方は何となく「ああそうかもねー」なんて思うふしがあるかもしれませんが、小学5年生って、3,4年生の頃から続いていた「中間反抗期」を抜け、少しずつ自分で判断したり行動したりということが増えていく年齢でもあります。
これは精神的な発達が若干遅めな発達障害児でも同じようで、息子も5年生の夏頃から徐々に「自分でやろうとする」「自分の判断で行動する」場面が増えてきました。
多少個人差はありますが、同じく発達障害児を持つママや彼らに関わるお医者さんやカウンセラーさんからも「5年生あたりから少し変わってくる」という話はよく聞きますね。
5年生って、学校からも「もう高学年の仲間入りだ」とか言われて下級生の面倒をみる機会があったり、委員会活動やクラブなどで6年生と一緒に行動する時間が増えたり、合宿(今はコロナの影響で出来なかったりしますが)があったりと、外的環境の刺激を受けることが多くなってくる学年です。
本人がそれほど意識していなくても周囲から5年生になった途端いきなり「高学年扱い」されるため、否応なしに少し「上の」世界に引っ張り上げられます。
「自分でやりたがる範囲が広がってきた」「こうしたい、という自分の意見が強固になってきた」「意思を通す理由に筋が通ってきた」
まだまだ子ども…と思っていたのに、遠くから友達と戯れるのを見ていたらひょっとした表情が中学生のように見えた…ということが出てくることも。

11歳ですからね。ティーンエイジャーの仲間入りをしたんだな、ということを親が痛感させられる年代になったのですからそれも当然なのかもしれません。
なぜ5年生から自立訓練なの?
5年生は自立要素の強い取り組みが学校でも多くなっていきます。
家庭科という実生活に沿った教科が始まり、英語はワンフレーズ覚えればよかったものから自己紹介や相手の好みを聞く、などのコミュニケーションをとる単元になっていきます。(2020年の公立小学校の場合)
国語や算数、社会なども自分の意見を発表したり、他人と討論して展開していくような指導内容に変化してきます。(もちろん息子は「全然興味ないから参加しない」か、「我が持論を聞け、民よ」と演説ぶっ放しているかのどちらかだそうですが…。)
今までは学年単位で動いていたものが、「委員会」や「クラブ」など学校全体に関わる活動や異学年交流も始まります。5年生で合宿を計画する小学校もありますね。
スポーツや合唱などの運動・文化活動を通して他の小学校と交流することもあるでしょう。
一気に世界が広がるわけです。
そして今まで何とも思わなかった自分の家庭の考え方を友達の家庭と比較し「なぜそうなのか」と問いただしてきてみたり、「自分はこうしたい!」と強く要望してきたり。
定型発達ではないのに、こんな場面は定型発達児を追いかけるようにしてすぐにやってきます。
不思議だなー…。でもかんしゃく起こしたり多動だったりはあんまり変わらないんだけれど…。ここら辺はゆーっくり発達するんでしょうねえ。(;一_一)

そんなわけで堰を切ったように芽生えてくる「自立心(に非常に近いヤワな自立心)」。(^_^;)
こんな様子が見てとれたら、自立訓練始まり!の合図です。
「興味を持った」その瞬間から始める
「今日家庭科でボタンつけをしたんですよ。息子くん、お裁縫好きなんですね。熱心に授業終わっても(算数の時間になっても社会の時間になっても)やっていました」
とある日担任の先生からお話されました。
褒めてもらっていたんですが、何だか手放しで褒められないような、微妙なお話内容なのですが…。

やろうとするだけでもすごいと思います。
初めから挑戦せずに「棄権!」は彼のあるあるなのですから。
そこで早速、おうちでパパのワイシャツのとれかけボタンを直してもらいました。
「ボタン付け、上手なんだって?先生から褒められたよー。一生懸命やってたんだってね。これも付けられるかなー?」
そう話すととても自慢気な顔で「えーでもぐちゃぐちゃになるよー?」
言いながら本当にぐっちゃぐちゃにこんがらかった状態ながらも付けてくれました。
「ほらねー。ぐちゃぐちゃでしょー?」
頭の中ではもっと上手にできる自分がいたのでしょう。出来上がりの状態にかんしゃく寸前の顔。私が褒めてもあまり効果がありません。

そこにちょうど帰ってきたパパ。「え?息子くんが付けたの?すごいじゃん!パパなんか玉結びもできないよ。ママにいつもやってもらうんだ。えー、すごいなあ、こんなことも出来るようになったのかあー」
第三者の誉め言葉に「でもぐちゃぐちゃなんだ…」
そう言いながらもかんしゃくは堪えた様子でした。
優しいパパはぐちゃぐちゃの糸のまま、次の日そのワイシャツを着て出勤。その様子を口に出さないながらも横目で確認していた息子。
パパがぐちゃぐちゃの状態のまま出勤したことで、「成功体験」にはならなかったけれど息子は「自分だってできる、という能力を認められた」と感じたようでした。
新しく習い始めたら即座に家庭でやらせてみる
その後家庭科で「ゆで卵」を習ってきたので、次の日一緒にゆで卵を作って夕飯に出しました。
家庭科で次はご飯を炊くから先にやってみたい、と言って事前にやったこともあります。
そこから徐々に電子レンジを一人で設定してみる、野菜を切る、炒める、という調理をやり始め、洗濯機を回す、ゴミを分別する、シーツを取り換える、などの生活で必要な家事をやるようになりました。
もちろん今でもかんしゃく持ちで気が散りやすいADHDで自閉症スペクトラムな息子、途中でかんしゃく勃発させて放り出したり、やってることそっちのけで本を読み始めたりでなかなか「仕事を完了」させられないことも多々ありますが(多々というか殆ど??)、それでも「やろうという気がおきて」「取り掛かる」ことはできるんだから、それで良しとするかな、と思ってみています。
「やる気があって」「取り掛かれる」。
まあそれで「自立訓練」は十分ではないでしょうか。

定型発達のお友達は、一人でバスにのって塾に行って帰ってくる、遠方の祖父母の家に弟を連れて新幹線で遊びに行く、留守番の間にインスタントラーメンを妹に作ってあげる、なんてことをやってのけるようですが。
「自立」の内容はその家庭それぞれなので、あまり気にしないようにしています。
まとめ
ただでさえ依存心の強い発達障害児。
自分で「やってみようと思う気力」と「実際にやってみる行動力」。これさえあれば、いざというときは結構なんとかなるものなんじゃないかと私は思っています。
この間は宅急便がくる時間に出席しなければならない地域の会議があったので、試しにハンコを渡して留守番を頼んでみたのですが。(インターホンのモニター見れば宅急便屋さんの制服分かるから判別できるよね?とは一応言っておきました。)
帰ってきたらちゃんと荷物は受け取っていて、しかもクール宅急便だったので冷暗所に運んでいました。
我が家のインターホンは、インターホン越しにちゃんと通話ボタンを押して通話しないとボタンが点滅するようになっているのですが、それも普通に通話したようです。
頼んだ私の方が、普通に出来ていたことに度肝を抜かれました。パパなんて成長を感じて寂しくなったようで泣いていましたよ。(ー_ー;)
子どもに「やる気」を感じた瞬間を見逃さず、すぐに実践させてみる。
発達障害だって、タイミングさえ合えば出来るよ!そう思います。
それが一つの小さな自信になっていったら…。君たちの笑顔はもっともっと増えるよね?
頑張れ、発達障害児!出来ないときはママがいつでも手を貸すからね!
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。